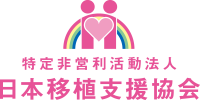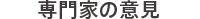|
筑波大学附属病院 2012年 |
脳死について
人の死―脳死と心停止
古くから、医師が人の死を確認するときには、心停止、呼吸停止、瞳孔散大の三徴候を確認してきましたし、現在でも多くの場合はそのようにされています。では脳死の場合にこれらの徴候はどうなっているのでしょうか。実は、心臓だけはまだ動いていますが、呼吸停止と瞳孔散大はすでにおこっているのです。呼吸をしていない状態が続けば、通常は間もなく心停止に移行します。医療技術の進歩によって人工呼吸を継続して行えるようになった結果、このような脳死状態が時にみられるようになってきました。脳死は、人工呼吸をすることによって心停止までの時間が引き延ばされた状態とも考えることができます。
脳死と植物状態
強い脳障害のあとに、意識が回復しない植物状態と呼ばれる状態になることがあります。外界からの刺激に反応することができないという点で脳死と混同される方もいらっしゃるかもしれません。では脳死と植物状態は、何が違うのでしょうか。その違いを理解するのに意識とは何かを考えてみましょう。意識は、『覚醒』と『認識』という二段構造になっているといわれています。このうち『覚醒』の維持に脳幹が、『認識』の維持に大脳が重要な役割を担っています。脳死も植物状態も、大脳が機能しない状態にあるので、物事を認識することはできません。脳死の場合は、大脳だけでなく脳幹も含めて脳の全ての機能が失われた状態ですので、決して覚醒することはありません。脳幹が担っている自発呼吸も停止していますので、人工呼吸器を外せば心臓の動きもすぐに止まってしまいます。一方、植物状態の場合、大脳は機能していませんが、脳幹機能が部分的にせよ働いていますので、覚醒リズムは保たれて開眼することもありますし、基本的に自発呼吸も保たれています。
脳死とされうる状態
脳神経外科診療の中では、重症のくも膜下出血や頭部外傷などによって強い器質的脳障害に陥ることがあります。どんなに強い刺激を加えたとしても眼を開くことも体を動かすことも全くみられない深昏睡になり、さらに自発呼吸が停止した状態の場合には、次に瞳孔所見を確認します。瞳孔が散大・固定しており、さらに種々の脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射、および咳反射)が消失していると、脳の機能が大脳だけでなく脳幹部まで失われた可能性が高くなります。
臨床経過や画像診断、脳波が平坦化しているなどの情報から総合的に判断し、適切な治療をすべておこなったとしても回復の可能性がないと考えられる場合に『脳死とされうる状態』という診断をします。現在では『臨床的脳死』という表現は使用しません。
法的脳死判定
『脳死とされうる状態』と判断され、さらに脳死下臓器提供に進む場合には、2名以上の判定医によって法的脳死判定を2回行います。2回目の脳死判定は、1回目の脳死判定が終了した時点から6歳以上では6時間以上、6歳未満では24時間以上経過してから行います。臓器提供を前提としない『脳死とされうる状態』の診断も、原則として法的脳死判定の項目、方法に準じて行われますが、無呼吸テストだけは身体への負担が大きいために法的脳死判定以外では必須ではありません。
小児脳死判定における注意点
小児の脳死判定で最も注意を要することは、被虐待児の対応です。法的脳死判定マニュアルでは、『被虐待児、または虐待が疑われる18歳未満の児童』は法的脳死判定から除外するよう規定しています。第三者目撃のない外傷の場合には、虐待を完全に否定することは容易ではありません。児童相談所、保健所、福祉事務所、子ども家庭支援センターなどの関係機関への過去に虐待の報告がなかったかどうか照会を行ったうえで、複数の医師、看護師、コメディカルスタッフから組織される院内虐待対応チームによって慎重に検討しなければなりません。脳死下臓器提供事例の報告書で脳死原疾患を年代別にみてみると、10代の実に75%が頭部外傷で、他の年代よりも頭部外傷の比率が明らかに高いのです。小児の脳死判定では院内虐待対応チームの迅速な招集、情報収集、判断という総合力も求められるのです。