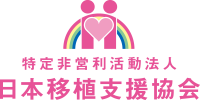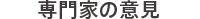|
独立行政法人 |
我が国では1997年に臓器の移植に関する法律が成立し、脳死患者から移植用臓器の摘出が可能になりました。脳死の診断法そのものは日本脳波学会による公表が1974年で、これは世界的にみて決して後れを取ってはいませんでしたが、米国や欧州では1970~80年代に脳死への法的対応が社会的になされたので、我が国の法的対応は遅れたと言えます。そして改正臓器移植法(2009年)によってご家族の承諾にて脳死下臓器提供が可能となりました。
さて、これで欧米と肩を並べたかと言えば、我が国に固有の大きな特徴があります。それは「臓器提供に繋がらないなら脳死による死亡宣告はあり得ない」という特殊事情です。脳死が全て人の死であれば「脳死後に移植用臓器を摘出する」は「心停止後に腎臓を摘出する」と同じですが、臓器移植に係らない脳死は患者の死亡ではありません。筆者は重症な脳外傷や脳卒中などの診療を経験してきました。医学はサイエンスですから私たちはそれを真摯に遂行しますが、同時にご家族の心情を慮ることも重要です。脳の蘇生がままならない状況に陥れば、脳死の病態を説明しますが、この時も同様です。
ここで我が国の特殊事情に戻りましょう。患者が脳死状態に陥ったことをご家族が理解したとしても、それのみでは死亡となりません。ドナーカードがあっても最終的にはご家族の判断です。つまり、ご家族は臓器提供を決めるなら、同時に患者の”脳死による死亡”を選択せねばなりません。脳死がそのまま人の死なら、引き続いて臓器摘出の諾否を決めればよいのですが、我が国はそのようではありません。脳死による死の選択によって、ご家族が「持続していた命を遮断すること」にあたかも与したかのごとき自責の念に”時を経て”悩む事例もあると聞きます。その心痛は如何ばかりかと思います。そこで、我が国の特殊事情のままでも例えば、人の存在は個々別々のようで実は同時に共同態を担っているという倫理学的考察などに倣って、脳死になれば皆が臓器提供を基本とするオプトアウトのルールを仮に実現するなら、死の選択に伴う悔恨の情が後々生じることはないようにも思われます。
そもそも人は自ら死を決められないので、”選択”もあり得ないとの法的見解もあるようです。しかし、法律などはその国の歴史や風土、文化に則ってルール化されるはずで、我が国の脳死下臓器移植もこのようにして今日に至っています。皆様のお考えはどのようでしょうか。